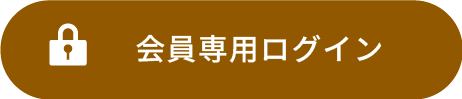産婦人科の進歩
次号掲載予定の最新論文
原 著
異所性妊娠における多量出血症例のリスク因子に関する検討:当院での手術症例132例における後方視的検討
| 著者・共著者: | 福田 大晃,磯野 渉,南野 有紗,新垣 亮輔,野口 智子,林 子耕 |
|---|---|
| 所 属: | 紀南病院産婦人科 |
受付日 2024/4/19
【目的】手術により治療した異所性妊娠の症例に関して,腹腔内出血が500 mL以上となる症例 を多量出血と定義し,そのリスク因子を抽出するために後方視的に検討した.【方法】2007年1月から 2023年12月に治療した140症例について,メトトレキサート療法などを施行した8症例を除外して,手 術を行った132症例を解析の対象とした.その中で,腹腔内出血量が500 mL以上の多量出血22症例の 臨床的傾向を解析するために,年齢,分娩歴,最終月経からの推定妊娠週数,尿中ヒト絨毛性ゴナド トロピン値,臨床症状(腹部症状,性器出血)などの因子を抽出した.【結果】推定妊娠週数,卵管膨 大部妊娠,腹部症状,性器出血,異所性胎囊所見,腹腔内液体貯留所見に関して,多量出血の22症例 と出血量500 mL未満のコントロール110症例で有意差があった.次に該当する因子を収集できた68症 例での多変量解析では,多量出血症例の可能性は腹部症状で有意に多く,卵管膨大部妊娠で有意に少 なく,妊娠7週以上,尿中hCG値4,000 mIU/mL以上で多い傾向にあった.【結論】腹部症状があり, 妊娠7週以上,尿中hCG値4,000 mIU/mL以上の症例では多量出血のリスクが高い傾向があり,より慎 重な対応が必要であると考えられた.〔産婦の進歩77(1),2025(令和7年2月)〕
キーワード:異所性妊娠,推定妊娠週数,腹部症状,多変量解析,後方視的研究
原 著
胚盤胞到達速度が出生児性比と出生体重へ及ぼす影響
| 著者・共著者: | 姜 賢淑,山出 一郎,中山 貴弘,眞田 佐知子,井上 卓也,濱田 啓義,澤田 守男,畑山 博 |
|---|---|
| 所 属: | 医療法人財団 今井会 足立病院 産婦人科 |
受付日 2024/4/10
目的:多くの哺乳類では,XY胚はXX胚よりも胚盤胞への発育速度が速いことが知られている.生殖補助医療では,胚盤胞へ速く到達した胚は妊娠率や生児獲得率の高い良好胚とされ,発育速度は移植胚選別の重要な指標である.通常培養では,Day5で胚盤胞に到達する胚(Day5BL)が最多だが,Day4で到達する胚(Day4BL)や,Day6で到達する胚(Day6BL)も存在する.これまでDay5BLとDay6BLとの比較で出生児性比に差がないという報告はあるが,Day4BLとDay6BLとの比較検討は見られない.当院での凍結融解単胚盤胞移植で,胚盤胞到達速度と出生児性比や出生体重の関連について検討した.方法:2014年1月から2023年7月における19,063例の凍結融解単胚移植のうち,305例の生児を対象とした.Day4BL群とDay6BL群における臨床背景,児の性別および体格を比較検討した.結果:Day4BL群とDay6BL群の間において出生児性比や出生時体格に有意差はなく,胚盤胞到達速度による影響は見られなかった.以上のことからDay6BLも移植胚選定において有効な選択肢と考えられた.〔産婦の進歩77(1),2025(令和7年2月)〕
キーワード:Day4胚盤胞,Day6胚盤胞,出生時性比,出生体重,傾向スコアマッチング
原 著
産科危機的出血に対する経カテーテル的動脈塞栓術の有用性に関する検討
| 著者・共著者: | 坂本 敬哉,川﨑 薫,城玲 央奈,森内 芳,黄 彩実,葉 宜慧,松村 謙臣 |
|---|---|
| 所 属: | 近畿大学医学部産科婦人科学教室 |
受付日 2024/1/12
当院で2012年から2022年に産科危機的出血に対し経カテーテル的動脈塞栓術(transcatheter arterial embolization;TAE)を施行した35症例を対象とし,TAEの臨床的成功率,不成功のリスク因子や合併症について後方視的に検討した.産科危機的出血の内訳は分娩後24時間以内の異常出血では弛緩出血(63%),後期分娩後異常出血では遺残胎盤(73%)が最も多かった.TAEの臨床的成功率は94%であった.分娩後24時間以内の異常出血では,再出血群(2例)と非再出血群(22例)とで妊娠と分娩方法,周産期合併症(妊娠高血圧症候群,産科DIC)の有無,臨床所見や血液検査所見に差はなかった.TAE不成功2例は弛緩出血と軟産道裂傷の合併,子宮型羊水塞栓症であり,1例は再TAE,1例は子宮摘出により止血した.合併症は発熱(37%),感染(20%),血管損傷(3%)であった.感染症のリスク因子は同定されなかった.TAEの成功率は高いが,TAEで止血しなかった場合の止血処置を念頭におく必要がある.そして造影CTは止血部位の同定や止血方法の決定に有用である.〔産婦の進歩77(1),2025(令和7年2月)〕
キーワード:産科危機的出血,経カテーテル的動脈塞栓術
症例報告
緊急帝王切開術後の絞扼性腸閉塞に対して腹腔鏡下腸管癒着剥離術を施行した1例
| 著者・共著者: | 植田 真帆1),田中 絢香1),山田 芙由美1),角田 紗保里1),八田 幸治1),高山 敬範1),山下 晋也2),橋本 奈美子1) |
|---|---|
| 所 属: | 1)日本生命病院産婦人科 2)同・消化器外科 |
受付日 2023/12/28
帝王切開術後の絞扼性腸閉塞はまれであるが,診断が遅れると腸管壊死をきたすため早急な対応が必要である.今回われわれは,腹腔鏡手術によって小腸閉塞の解除を行なった1例を経験したので報告する.症例は40歳2経1妊の経産婦であり,既往帝王切開術後妊娠に対して選択的帝王切開術予定であったが,妊娠37週4日に陣痛が発来したため緊急帝王切開術を施行した.術後3日目の夜間より左側腹部痛が出現し,術後4日目朝に腹膜刺激症状と血液検査で炎症反応を認めた.腹部X線検査で小腸の拡張とニボーを認め,腹部造影CT検査で小腸の拡張と回腸遠位の狭窄を認めた.絞扼性腸閉塞と診断して緊急腹腔鏡下腸管癒着剥離術を施行した.術中所見では子宮底部と腸間膜の間に索状物を認め,索状物により小腸が絞扼していた.腸管虚血には至っておらず,索状物を切離して閉塞を解除して手術を終了した.術後経過は良好であった.産褥期の腸閉塞の半数以上は既往手術による癒着が原因とされている.本症例は腸閉塞を疑い,早期診断ができたため腹腔鏡手術が可能であった.帝王切開術後に限局した強い腹痛を認めた場合には,絞扼性腸閉塞の可能性も考慮して診療にあたる必要がある.〔産婦の進歩77(1),2025(令和7年2月)〕
キーワード:絞扼性腸閉塞,帝王切開術後,腹腔鏡下腸管癒着剥離術